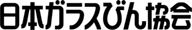ガラスびんの歴史
ガラスびんの歴史
-
紀元前3000年頃国外
メソポタミア・エジプトでガラス細工(丸玉、管玉)がつくられる
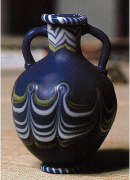
-
紀元前1500年頃国外
コア技法によるガラスの器(香油びん)がつくられる
「容器のはじまり」となる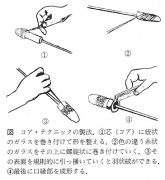
-
紀元前100年頃国外
鋳造技法によるガラスの椀や板ガラスの製造
-
紀元前30年頃国外
吹き技法によるガラス容器の製造
-
700年頃国外
クラウン法による板ガラスの製造
-
14~16世紀国外
レンズ(眼鏡)、ガラス鏡、顕微鏡、望遠鏡などが発明
-
1549年国内
フランシスコ・ザビエルが鹿児島に来訪。時計、眼鏡、遠眼鏡などが贈られる
びいどろと呼ばれる -
1650年頃国外
コルク栓が大量に使えるようになり、ビールびんやワインびんの利用が急速に広がる
-
1690年国外
アメリカで初のガラスびん工場ができる
-
1755年国内
播磨屋清兵衛(はりまやのせいべい)が、国内にガラス技術を広める
和製びいどろと呼ばれる -
1791年国内
世界初の合成ソーダ製造法「ルブラン法」発明
-
1700年代後半
〜1800年代中頃国内国内にヨーロッパの高級ガラスがもたらされ、鉛ガラスからソーダ石灰ガラスに代わる
ギヤマンと呼ばれる -
1804年国外
ニコラ・アペールが、ガラスびんの中に食物を入れて密封、加熱殺菌して保存する
食料貯蔵法を発明 -
1830年頃国内
びん詰め清酒が出回るようになる
-
1849年国外
イギリスでガラス玉内蔵びん(ラムネびん)発明
-
1850年国外
アメリカで連続式ガラス溶解炉完成
-
1857年国外
「蓄熱式加熱法」の発明。るつぼ窯から連続溶融のタンク炉へ
-
1863年国内
合成ソーダ灰の新製造法「ソルベー法」発明
-
1867年国外
「蓄熱室付き連続溶融タンク炉」の開発。現代の溶融炉の基礎となる
-
1870年頃国内
ビールや洋酒などの輸入が始まり、空きびんをリユースして使うようになる
-
1876年国内
官営の品川硝子製作所が設立。国内のガラスびんの工業化が始まったが、すぐに閉鎖となる
-
1885年国外
イギリスでブロー・アンド・ブロー方式製びん機を発明
-
1889年国内
初の国産ビールがつくられる
容器はガラスびん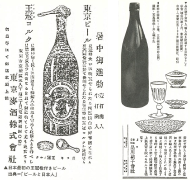
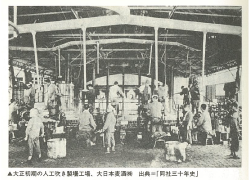
-
1893年国外
プレス・アンド・ブロー法半自動機で広口びんを製造
-
1916年国内
アメリカのオーエンス社製自動製びん機の国内導入
-
1924年国外
アメリカのハートホート社が自動製壜機「IS(Individual section)マシン」を発明
-
1952年国内
全自動製壜協会設立(現在の日本ガラスびん協会)
-
1953年国内
軽量法改正により「丸正びん」(一升びん・ビールびん・牛乳びん)が登場
-
1957年国内
協会名を日本自動製壜協会に改称
-
1960年国内
自動製壜機「ISマシン」の日本導入
-
1960年頃国内
スクリュー口を開発
-
1969年国内
協会名を日本製壜協会に改称
-
1973年国内
ガラスびんメーカーがびんリサイクルの取り組みを始める
-
1984年国内
ガラスびんリサイクリング推進連合設立
-
1986年国内
協会名を日本ガラスびん協会に改称
-
1991年国内
カレットの使用率が50%を超える
統一規格リターナブルびん「Rマークびん」が登場しシンボルマークの「Rマーク」を商標登録 -
1996年国内
ガラスびんリサイクル促進協議会設立(現在のガラスびん3R促進協議会)
-
1997年国内
容器包装リサイクル法が施行。消費者と市町村と事業者が役割を分担して、
空きびんの分別収集・リサイクルに取り組むことが義務づけられる -
1998年国内
カレットの使用率が70%を超える
-
2000年国内
「超軽量びん」の定義と算定方式を定め、シンボルマークを商標登録
「エコロジーボトル」「スーパーエコロジーボトル」の定義を定め、シンボルマークを商標登録
生協団体で構成する「びん再使用ネットワーク」が超軽量Rマークびんを開発 -
2001年国内
ガラス産業連合会(前年発足のガラス産業協議会を改称)に加盟
-
2003年国内
カレットの使用率が90%を超える
日本ガラスびん協会のシンボルマークを制定 -
2004年国内
「ガラスびんデザインアワード」はじまる
-
2007年国内
ガラスびんリサイクル促進協議会が「3Rのためのガラス容器自主設計ガイドライン」を発表し、
分別排出の基準を公開 -
2008年国内
リターナブルびん使用におけるCO₂排出量削減試算報告書を作成し説明会を実施
-
2009年国内
ガラスびんデザインアワードを「ガラスびんアワード」にリニューアル
-
2014年国内
ガラスびんリサイクル促進協議会がガラスびん3R促進協議会に改称
-
2021年国内
「ガラスびんSDGs表明」を宣言
ガラスびん3R促進協議会がびんリユースシステムのライフサイクル分析を実施 -
2022年国内 国外
協会設立70周年記念誌エシカルパッケージ「ガラスびんSDGs読本」を発行
国連総会で国際ガラス年が採択 -
2025年国内
「(自主認定)ガラスびんリサイクルマーク」を制定し運用開始
画像出典:「日本の板ガラス」板硝子協会、「ガラスの博物誌」中近東文化センター 2005
参照:「ガラスの百科事典」朝倉書店 2007